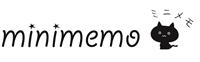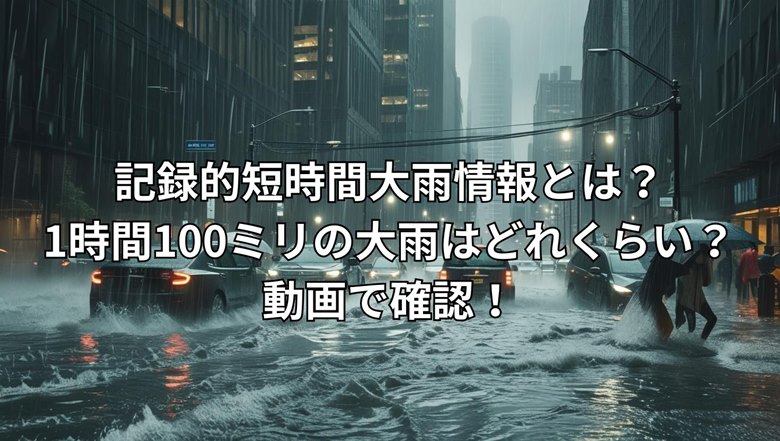「1時間に100ミリの雨って、実際どれくらいのものなの?」と疑問に感じたことはありませんか?
近年、日本各地で発生している短時間の猛烈な雨。
その中でも「1時間に100ミリ」という雨量は、気象庁が、“恐怖を感じるような雨”と表現するほど危険な雨のレベルです。
1時間に100ミリ級の雨ともなると、気象庁が「記録的短時間大雨情報」を発表することがあります。記録的短時間大雨情報は「数年に一度」レベルの非常に激しい雨に対して出され、災害発生の危険性が極めて高いという警告です。
動画でわかる!猛烈な雨の恐ろしさ
1時間に100ミリの雨とは、どれほどすさまじいものなのか。
百聞は一見にしかず、ということで、実際の映像をご覧ください。
自動車が今にも全部水没してしまいそうです。
1時間に100ミリの雨はどれくらいの量か?
1時間に100ミリの雨はどれくらいの量なのかについて、詳しく解説していきます。
①「猛烈な雨」に分類される理由
気象庁によると、1時間に80ミリ以上の雨は「猛烈な雨」と分類されます。
この区分の中でも100ミリは最上級クラスに位置しており、まさに“恐怖を感じるレベル”です。
滝のように降りしきる雨は、すでに傘では太刀打ちできず、建物の中にいても不安になるほどの音と圧力を伴います。
この猛烈な雨は、短時間でも甚大な被害を引き起こす可能性が高く、土砂災害や都市型水害の大きな要因になります。
気象庁では、「命を守る行動が必要な雨」として、非常に強い警戒を呼びかけています。
「猛烈」という言葉がぴったりすぎるような怖さの雨です。
②傘もワイパーも役に立たない雨の勢い
実際に100ミリの雨が降ると、まず傘がほとんど無意味になります。
強風を伴わなくても、雨粒が大きく激しく打ちつけてくるため、傘は破れそうになるか、すぐに中まで濡れてしまう状態に。
車に乗っていても同様で、ワイパーを最速にしても視界が確保できないほどの雨がフロントガラスを打ちつけます。
これは実際に山口市の消防本部職員の証言にもあり、「とても運転できる状況ではなかった」とのこと。
街中のマンホールが水圧で吹き上がることもあり、見た目も音も恐怖感をあおります。
まさに“自然の力に押しつぶされそうになる”感覚とも言えるものです。
③実際に体験した人のリアルな声
2013年7月の山口県や東京都目黒区で発生した豪雨では、住民や現場職員から多くの証言がありました。
「今まで経験したことのない雨だった」「あっという間に道路が川のようになった」といったコメントが相次いでいます。
特に消防職員は、「傘が破けそうな勢い」「排水溝から水が噴き出していた」と証言。
これらの声から、単なる“大雨”ではなく、命の危険が現実に感じられるほどの状況であったことが伝わってきます。
また「家の中にいても不安だった」「避難しようにも外に出られなかった」という声も記憶に残るものです。
④1時間で10cmの水たまりができるって本当?
「100ミリの雨」というのは、単純に言うと“地面に10センチの水が溜まる”ということです。
これは「降水量=水深」の意味であり、地面に染み込んだり流れ去らなければ、10cmもの深さの水が1時間で積もる計算になります。
たとえば、ベランダやアスファルトの道路では水が逃げないため、そのまま溜まりやすくなり、瞬く間に冠水状態になる可能性があります。
つまり、人の足首を完全に覆うほどの深さになるということ。
もう、水たまりじゃなくて“池”レベルということもできるのです。
⑤身の危険を感じるレベルの大雨とは
気象庁が「恐怖を感じるような雨」と表現しているように、1時間100ミリの雨はまさに命にかかわる状況です。
この雨量になると、小さな川は数分で氾濫し、アンダーパスや地下空間は急激に水没します。
都市部では地下鉄や地下街の浸水、住宅地でも床上浸水、さらには土砂崩れや道路の陥没まで…。
想像するだけでぞっとしますが、実際に毎年のようにこのレベルの雨で大災害が発生しています。
一瞬でも油断したら取り返しがつかない、そういう雨だということができます。
⑥100ミリの雨が降ったときの都市の様子
東京都目黒区や世田谷区で1時間100ミリの雨が降った際、街中の道路は完全に川のような状態に。
マンホールからは水が噴き出し、低地では排水が追いつかず、大規模な冠水が発生しました。
地下の構造物にも浸水被害が広がり、電車の遅延や商業施設の一時閉鎖など、都市機能もマヒします。
それに加えて、雨音があまりに大きいため、警報音や人の声もかき消され、避難にも支障が出ることがあります。
とくに都市部はアスファルトで覆われているから、水の逃げ場がないということもあるのですね。
⑦他の雨量と比較してみたインパクト
雨の強さを比較すると、以下のような段階があります。
| 雨の種類 | 降水量(1時間) | 状況例 |
|---|---|---|
| やや強い雨 | 10~20mm | 水たまりができる |
| 強い雨 | 20~30mm | 土砂降り、傘が効かない |
| 激しい雨 | 30~50mm | バケツをひっくり返したよう |
| 非常に激しい雨 | 50~80mm | 滝のよう、先が見えない |
| 猛烈な雨 | 80mm以上 | 恐怖、避難が必要 |